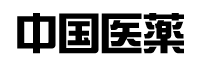2020/12/3 ウェビナー 「生の中国 / 新薬の臨床開発·事業化」
この度、「新薬・日中未来」セミナー研究機構を立ち上げました。ここ数年、一気に、多彩な変化を遂げつつある中国。断片的な情報は得られても全体の繋がりが分からない、その全体像を捉えるのが非常に難しいといった声を耳にします。そう […]
弁理士 (川本バイオビジネス弁理士事務所(日本)所長、大邦律師事務所(上海)高級顧問)
藤沢薬品(現アステラス製薬)で知財の権利化・侵害問題処理、国際ビジネス法務分野で25年間(この間、3年の米国駐在)勤務。2005年に独立し、川本バイオビジネス弁理士事務所を開設(東京)。バイオベンチャーの知財政策の立案、ビジネス交渉代理(ビジネススキームの構築、契約条件交渉、契約書等の起案を含む)を主業務。また3社の社外役員として経営にも参画。2012年より、上海大邦律師事務所の高級顧問。現在、日中間のライフサイエンス分野でのビジネスの構築・交渉代理を専門。仕事・生活のベースは中国が主体、日本には年間2-3か月滞在。
この度、「新薬・日中未来」セミナー研究機構を立ち上げました。ここ数年、一気に、多彩な変化を遂げつつある中国。断片的な情報は得られても全体の繋がりが分からない、その全体像を捉えるのが非常に難しいといった声を耳にします。そう […]
医薬品の分野が、米中間で政治問題化している通信・IT分野と異なっている所は、中国が医療分野で大きな国内問題を抱えていており、その制度改革と表裏一体の関係にあることです。医薬品の流通、薬価、保険、製品の品質等の問題がそれです。
この記事では改革の方向性や知財制度改正の3つのポイントを取り上げます。
BeiGene (百済神州)のBTK阻害剤である zanubrutinib が FDA によって画期的治療薬として指定を受けました。今後 zanubrutinib は各申請を省略し、上市申請されることになります。また、こ […]
Innovent Biologics(信達生物)のがん免疫療法薬 Tyvyt (sintilimab) が、12月27日に上市承認されました。これにより、中国で上市承認された中国発の免疫療法薬は2つとなりました。 中国において既に上市されている抗PD-1/PD-L1阻害剤は、中国発2つ、海外発2つで、Innovent の CEO は PD-1 阻害薬が中国の医薬品企業にとって海外企業と対等に戦うことのできる最初の領域になったと語っています。
12月5日、李克強総理は国務院常務会議を司会、《中華人民共和国特許法改正案(草案)》(中国語:中华人民共和国专利法修正案)を可決し、草案を2018年12月23日〜29日に開催予定の全国人民代表大会常務委員会に提出することを決定しました。今回国務院を通過したこの特許法改正案には3つの注目点があります。
経済的にも国の生き残りをかけて党・行政主導による産業構造の未来に向けた改造に向かっている中国。医薬品産業においては、過去数年、ジェネリックの事業環境に大鉈が振るわれ、且つ、新薬の研究開発の推進に向けて重点的な梃入れ政策が打たれています。
そのような中国における医薬品産業を取り巻く激動が渦巻く今、中国の医薬品企業は、どのような企業戦略でこの環境を乗り越えようとしているのでしょうか? さらに、中国の政策・規制環境は将来、どちらに向かっていくのでしょうか? 今後、日本の医薬品企業が中国とどのように向き合っていったらよいかを考えていただくために、一石を投じたいと思います。
日本の総理大臣が7年ぶりに中国を公式訪問した10月26日、52本の協力覚書が交換されました。 そのうちの一件として、富士フイルムと中国の浙江海正との、抗インフルエンザ薬「アビガン」に関する提携の覚書があります。
新薬の初上市を中国でするケースが増えてきました。中でもアストラゼネカは世界で販売予定の貧血治療用新薬をまず中国で米国より1年ほど早く投入します。またイーライリリーも新薬を中国でまず上市予定です。背景には中国の市場の拡大と、制度の変化があります。
2018年5月に非臨床・臨床の試験データの保護制度に関する法案が公表されました。最長で12年の保護期間が与えられます。この記事ではこの法案の詳細について、またデータ保護政策の流れについて解説しています。
国務院常務会議において李克強総理は抗がん剤の関税をなくすと発表し大きな話題になりました。しかしよく調査してみるとこれだけではあまり実効性のある政策ではありません。他の2つの政策と組合せることによって、実効性と話題性を持たせることに成功しています。この政策の背景についても解説しています。
5月15日、日本経済新聞は「中国、薬の特許期間を延長 5年間、先進国並みに」という記事を掲載し、中国が5月から医薬品の特許期間を今の20年から最長25年間に延長し、先進国と足並みをそろえたと報道しました。しかしこの報道には若干修正が必要です。さらに詳しい情報をお伝えします。
昨年 2015 年 4 月に中国特許庁より公表され、パブリックコメントを募った改正法案に基づき、その改正の方向性について、中国特許法の第四次改正案(前半)にて説明致しました。近年、中国の政府及び国内企業が研究開発の投資を積極化していることを受けて、中国国内の研究機関に於いて、自主技術、自主知財の蓄積が大幅に進んでいます。更には、中国経済が「新常態」に入り、従来の労働・資源集約型の重厚長大産業を中心とした産業構造からの脱却、その為のイノベーションの推進政策に力点が移されています。そのような中国の経済環境の大きな変革の下、特許法の改正準備作業が進んでいると言えます。
開発(臨床開発を含む)による特許権の「使用」ですが、例えば、ジェネリック企業が第三者の有する特許でカバーされる新規特許医薬品をその有効期間中に開発(特許発明の実施)することは、特許権者の権利を侵害することになるのか? これについては、米国では、特許法271(e)(Bokar条項)により、非侵害行為、日本でも、特許法に明文の規定はないものの最高裁の判例により非侵害行為と考えられています。 さて、中国では。
今、第4次の特許法の改正に向けて議論が盛んです。前回の第3次の改正は、2009年になされました。それから6年が経過し、特許侵害訴訟の局面で、制度上の不備も指摘されています。中国で自主イノベーションの能力がある一定の水準に達しつつある今、イノベーションを軸に経済構造の展開を図らなければならない中国にとって、イノベーションを更に推進する為に特許制度の見直しが必須の情勢であるという社会的な背景があります。
ある基本技術Xについて、日本企業(ライセンサー)が中国で基本特許を有しており、当該特許に基づき、中国企業(ライセンシー)に契約地域を中国としてライセンス許諾がされることを想定してみましょう。中国企業のR&D能力が […]
新製品を生み出す為に必要とされる基礎技術がより広範に、そして、より高度になってきており、これら全ての基礎技術を自社で開発・獲得し、単独で新製品の創出をしていくことは、非常に難しい時代になってきています。そこで、世界的な潮 […]
中国では、4,5年前に中国の軍事医学科学院が見出したとされる抗エボラ・ウイルス薬JK-05について、四環医薬が技術移転を受け、臨床試験の開始を予定しているとの発表がありました。その後、日本の「アビガン」と中国の「JK-05」が実は同一化学成分である可能性があり、もしそうであれば、当該成分に関して、日本の富山化学が中国で特許を有していることから、四環医薬はその特許権を侵害することになるとの報道がされました。
第三者が自社の特許(実用新案権、意匠権も概念として含める)を侵害する製品を製造・販売している等の侵害行為をしている場合、その救済を求めるに当たり、中国では3つのルートがあり、中国特許法第60条以下に規定されています。先ず、①当事者の協議による解決を求めており、次いで②司法ルート及び③行政ルートで救済を求めることが出来るとしています。
日本では特許庁が特許の主管庁として出願を受理し、審査、特許権の付与の業務を行うと同時に、特許政策の立案を主導しています。一方で、知的財産権の侵害事件等は、裁判所での処理、即ち、侵害に対する停止、損害賠償の請求等の救済措置は裁判所で実現、解決を図っていく制度をとっています。さて、中国ではどうでしょうか?
日本側の声として、中国企業とライセンス契約を締結して、特許・ノウハウ技術のライセンスを許諾したけれど、一向に契約通りに履行してくれない。ライセンス契約上、中国企業(ライセンシー)から支払われる契約金(upfront mo […]