共同研究・委託研究と特許を受ける権利 / その視点の違い
1.特許を受ける権利と権利帰属
前回No.2では、職務発明の日中間の視点の違いを採り上げ、職務発明に関わる権利は、日本の特許法では発明者に帰属、一方、中国では発明者が所属する企業に帰属するとされていることに始まり(特許法§6)、発明者への報奨金等の支払いの考え方の説明をしました。ここで、職務発明に関わる権利と表現しましたが、この権利は、日本の特許法では「特許を受ける権利」と呼ばれています。会社で発明が生まれた場合、日本では、会社は、発明者から職務発明についての「特許を受ける権利」の譲渡を受けた上で、当該権利に基づいて、自己の名義にて、日本を含む各国に特許出願をします。会社は、「特許を受ける権利」を有する特許出願人として、各国特許庁で審査を受けます。 特許要件を満たしていると判断されれば、特許権が付与されて、会社は、特許出願人から特許権者へと立場が変わります。
このように「特許を受ける権利」は、発明者が発明を完成した時に生まれ、特許出願後、審査を経て、特許権が成立するまでを指す権利です。 さて、中国では、どうでしょうか?中国では、発明者が発明を完成した時に生まれる権利は「特許出願することが出来る権利」(申请专利的权利)です。 当該権利は、会社に原始的に帰属しますが、会社が特許出願をすれば、それ以降は、「特許出願権」(专利申请权)と呼ばれます。そして、特許が成立後は、日本同様、「特許権」です。 このように日本の「特許を受ける権利」は、中国では、二分した概念となり、前半の発明完成から特許出願までを「特許出願することが出来る権利」(特許法§6)、後半の、特許出願後、特許成立までを「特許出願権」(§10、§15)と呼びます。
発明は色々な枠組みから生まれますが、自社の研究所でなす自社研究、第三者との共同研究、第三者への委託研究(例えば、公的な研究機関、CRO等の研究受託企業への研究の委託)から生まれることが想定されます。其々の場合、法律上、当該発明の「特許を受ける権利」がどこに帰属することになるのか、を、我々は、押さえておくことが重要です。それが自社にとって不都合な場合に、相手方との契約によって、法律に従った帰属関係に修正を加えて、自己の有利なように、例えば、自社に帰属すると、契約で規定していくことが必要になってきます。
2.権利帰属 / 中国特許法
1)職務発明と権利帰属
中国法の下では、法律上、自社研究の場合(日系の中国子会社を含めた中国の企業が中国国内で研究する場合)、自社研究者の職務発明についての「特許出願することが出来る権利」は会社に帰属します(特許法§6)。 企業経営の視点に立てば、中国国内で自社研究を行う場合、職務発明である限りは、会社に帰属するので、権利の帰属については特段の問題なし。
2)共同研究と権利帰属
次に、中国で第三者と共同研究を実施する場合、法律上は、原則、両者の共有とされているものの、一方の会社の研究者のみが、発明の創造性(日本の進歩性の概念)の創出に寄与し、他方の会社の研究者の寄与がなく、ある一つの発明が完成した場合は、当該発明者を出している会社のみに権利が帰属するとされています(特許法§8、契約法§340)。 一方で、中国法には、当事者が共同研究契約等の中で、権利の帰属について規定したような場合には、当事者の合意が優先する旨、定められています(特許法§8)。従って、契約当事者の意向として、発明がどちら側の会社の研究員によって完成されようとも、特許権を両者の共有ということにしたいのであれば、若しくは自社で100%の権利を取得したいのであれば、その旨、両者間で合意し、契約で規定する必要があり、また、法律上も、当該合意が優先します。
3)研究委託と権利帰属
次に、中国で第三者の研究機関に研究を委託する場合、たとえ、委託者が研究費等の資金の全額を負担し、更には基礎となる関連情報・データを提供したとしても、受託者の研究者のみが発明者と認定されるような仕事をして新たに発明が完成されたような場合、法律上は、当該発明についての「特許出願することが出来る権利」は、発明を完成したもの、即ち、受託者に帰属することになります(特許法§8、契約法§339)。 しかしながら、当事者間にとって、それが不都合な場合、両者の契約によって、これと異なった権利帰属関係を約定することは、法律上、許されています。ですので、研究を中国の企業に委託する際、日本側が、中国の企業に対し当該研究をするに十分な資金を委託研究費として支払う場合には、日本側は、当然、「特許出願することが出来る権利」(特許を受ける権利)を含む成果物は日本側に100%帰属すると理解しているでしょうから、その旨、契約に明確に規定しておく必要があります。何も規定していなければ、発明をなした者、即ち、受託者の物となり、委託者は一切の権利を有しません。
中国では、1980年代以前は、全ての研究、発明は、国の計画経済に基づいて、国家が各研究機関に資金を提供し、一種の委託研究の形で、即ち、国が研究機関に研究を委託する形で、“全て”の研究がなされていました。もし、法律によって、研究の成果としての発明についての「特許出願することが出来る権利」は委託者に帰属する旨、定めてしまうと、全ての特許権が委託者としての国に帰属することになってしまします。それを避けるために、実際に発明をなした者、即ち、受託者に発明の権利を帰属させるとの原則が法律に明記されている、と、その歴史的な背景が説明されています。ただ、前記したように、これは、あくまでも、当事者間で、権利の帰属について契約で定めていなかった場合の話であり、契約で、権利は委託者に帰属すると定めてしまえば、当該当事者間の合意が優先します。
4)日中間の共同研究・研究委託契約に於ける権利帰属の規定
日本側が中国側に研究を委託する場合、様々な枠組みがあると思います。例えば、日本側で発明が完成しており、商品化に向けた実証データを取る(既に見出されて発明が完成している新規医薬化合物について、動物でのGLP毒性データを取る)といった場合、実証データは生まれても、発明が生まれることは、想定されていません。その場合、万一、発明が生まれたとしましょう。委託契約にその所有権の帰属について何ら定めがなければ、日本側が発明の創造性の創出に何ら寄与がない場合(日本側の研究者が発明者として認定されないような場合)、法律上、発明の「特許出願することが出来る権利」は、中国側に帰属することになります。 また、委託研究の目的となる当該データの帰属についても、契約に何ら約定がない場合、中国側が委託者と同等の使用権等を有することになります(契約法§341)。研究資金を全額、日本側が負担する場合であっても、何ら契約上の規定がない場合、中国側が当該発明の所有権を握り、且つ、データについては一定の使用権を有することになりますので、この点、留意して契約で、権利帰属・使用権について、明確に定めておく(日本側に帰属すると定める)必要があります。この点は、日本国内取引の実務でも当たり前のことだと思います。
尚、中国の企業・研究機関と日本企業間の委託研究契約、共同研究契約の準拠法が日本法の場合、上記の中国法の考え方の適用はないとも言えますが、中国企業・研究機関との契約の基本条件の枠組みの協議・ネゴ―シエーションに当たって、中国側の発想の出発点はどこにあるのかを知っておくことは、円滑に最終合意に持ち込む為にも非常に重要です。また、準拠法が契約交渉の最終段階で交渉の結果として、日本法でなく中国法が採用されるような場合も想定しておく必要があり、共同研究等の契約の1stドラフトの段階から、中国法の枠組を理解した上で、起案していくことが重要だと思います。また、共同研究契約を締結するにあたって、日本側から中国側への技術の導入が含まれている場合、更には共同研究の対象となる技術が中国政府が技術の導出入に規制をかけている特定の技術分野に関わるようなには、中国政府・商務局への届出が必要な場合もあるので、あらゆる場合を想定して、権利の帰属については、契約に明示的に規定しておくことが肝要です。
従来、日本企業は、日本・欧米の企業・研究機関のサイエンス・技術レベルの高さを反映して、共同研究の相手先は、日系、欧米系の企業であることが多く、共同研究契約の基本条件等の枠組みも、日本法、英米法の環境下に、思考していけば良かったように思います。然しながら、中国の企業・研究機関のサイエンス・技術面での台頭が予想される中、中国の企業・研究機関の存在も無視しえない時代が近づいてきており、中国法・規制、中国ビジネス環境下での制約等を視野に入れて考えていく時期に入ってきているように思われます。尚、共同研究の枠組み、更には、ライセンス契約下での研究開発活動の成果としての発明が日本側と中国側の共有、との合意がされることがありますが、特許権の共有について、日中間に考え方の違いがありますので、次回以降に説明したいと思います。
投稿者プロフィール
-
弁理士 (川本バイオビジネス弁理士事務所(日本)所長、大邦律師事務所(上海)高級顧問)
藤沢薬品(現アステラス製薬)で知財の権利化・侵害問題処理、国際ビジネス法務分野で25年間(この間、3年の米国駐在)勤務。2005年に独立し、川本バイオビジネス弁理士事務所を開設(東京)。バイオベンチャーの知財政策の立案、ビジネス交渉代理(ビジネススキームの構築、契約条件交渉、契約書等の起案を含む)を主業務。また3社の社外役員として経営にも参画。2012年より、上海大邦律師事務所の高級顧問。現在、日中間のライフサイエンス分野でのビジネスの構築・交渉代理を専門。仕事・生活のベースは中国が主体、日本には年間2-3か月滞在。
最新の投稿
 政策行政2026年2月13日中国の新薬データ保護・希少薬等の販売独占制度「医薬品管理法実施条例」公布
政策行政2026年2月13日中国の新薬データ保護・希少薬等の販売独占制度「医薬品管理法実施条例」公布 R&D新薬2025年9月29日新薬IND申請の迅速承認(30日)制度が正式に始動・中国薬事制度改革
R&D新薬2025年9月29日新薬IND申請の迅速承認(30日)制度が正式に始動・中国薬事制度改革 セミナー2025年9月25日中国バイオ医薬品産業セミナー 11月5日開催
セミナー2025年9月25日中国バイオ医薬品産業セミナー 11月5日開催 医薬市場2025年9月9日2025年:中国バイオ・新薬産業が潮目を変えた年
医薬市場2025年9月9日2025年:中国バイオ・新薬産業が潮目を変えた年
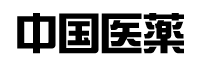


返信を残す
Want to join the discussion?Feel free to contribute!