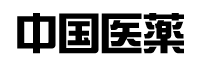中国産の発明 / 海外出願(中国国外への出願)
日本国内で生まれた発明は、どこの国で最初に特許出願をしようと、これは出願人の勝手です。米国の企業が、日本にある研究機関に研究を委託しそこから発明が生まれたと仮定しましょう。契約で当該委託研究から生まれた発明は米国企業に帰属すると合意していれば、米国企業は、最初の特許出願をどこでするのか自由に決定できます。一方で、米国国内で生まれた発明については、まず米国での出願が求められます。では、中国国内で生まれた発明についてはどうでしょうか?
弁理士 (川本バイオビジネス弁理士事務所(日本)所長、大邦律師事務所(上海)高級顧問)
藤沢薬品(現アステラス製薬)で知財の権利化・侵害問題処理、国際ビジネス法務分野で25年間(この間、3年の米国駐在)勤務。2005年に独立し、川本バイオビジネス弁理士事務所を開設(東京)。バイオベンチャーの知財政策の立案、ビジネス交渉代理(ビジネススキームの構築、契約条件交渉、契約書等の起案を含む)を主業務。また3社の社外役員として経営にも参画。2012年より、上海大邦律師事務所の高級顧問。現在、日中間のライフサイエンス分野でのビジネスの構築・交渉代理を専門。仕事・生活のベースは中国が主体、日本には年間2-3か月滞在。
日本国内で生まれた発明は、どこの国で最初に特許出願をしようと、これは出願人の勝手です。米国の企業が、日本にある研究機関に研究を委託しそこから発明が生まれたと仮定しましょう。契約で当該委託研究から生まれた発明は米国企業に帰属すると合意していれば、米国企業は、最初の特許出願をどこでするのか自由に決定できます。一方で、米国国内で生まれた発明については、まず米国での出願が求められます。では、中国国内で生まれた発明についてはどうでしょうか?
職務発明に関わる権利は、日本の特許法では「特許を受ける権利」と呼ばれています。会社で発明が生まれた場合、日本では、会社は、発明者から職務発明についての「特許を受ける権利」の譲渡を受けた上で特許出願人として各国に特許出願をします。その後、特許権が付与されて、会社は特許出願人から特許権者へと立場が変わります。さて、中国では、どうでしょうか?
会社時代、天然物の研究者の片腕?の役割で東南アジアのある国から新規医薬品の種となりうる微生物を豊富に富む土壌を入手する仕事を一緒にさせて頂いたことがあります。当時、友人であるその研究者が、中国のベトナム国境近く、雲南省の微生物が欲しいと呟かれて、では、次は雲南から、と思っていたのですが、それは実現せず、お蔵入り。手に入りにくいと、チャレンジ精神が掻き立てられる?のかもしれませんが、今回は、手に入りにくい背景、関連する特許法の枠組み・構成について、説明したいと思います。